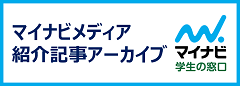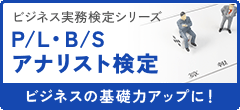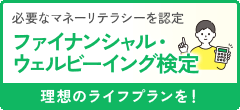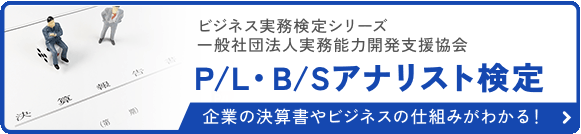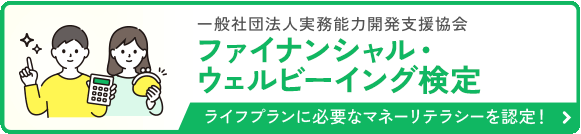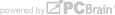企業様へのインタビュー
スポット社労士くん社会保険労務士法人
| 事業内容 | 社会保険労務士事務所 (専門・技術サービス業) |
| 企業規模 | 50名 |
| ホームページ | https://spot-s.or.jp/ |
<目的・動機>この検定を知ったきっかけや、社員に受験を推奨しようと思った目的・動機などについて教えてください。
当法人は、全国の中小企業を対象に、クラウドシステム「freee人事労務」を活用した給与計算・労務管理サービス「給与伴走くん」を提供しています。
給与計算業務は一見ルーティンのように見えますが、実際には毎月のように発生するイレギュラーな対応に対して、正確かつ柔軟に対応する力が求められる、高度な専門業務です。たとえば、
- 途中入退社に伴う日割計算の処理
- 遅刻・早退・欠勤控除の算出
- 育休・産休中の保険料免除や復職時の再適用
- 随時改定(月額変更届)の判定と反映
といった処理が、しばしば発生します。こうした業務に確実に対応するためには、単なる手順の暗記ではなく、法的根拠や計算の仕組みを理解した上での判断力が必要不可欠です。
「給与計算実務能力検定」は、そうした実務の背景や根拠を体系的に学ぶことができる非常に優れた資格です。単なる知識の習得にとどまらず、実務経験者にとっても、知識の整理や論理的な理解に役立っており、業務の精度向上だけでなく、自信にもつながっています。
私たちは、2030年までに全国3万社の中小企業の労務支援を実現することを目標に掲げています。そのためには、高品質な実務力を備えたスタッフの育成が欠かせません。外部からもスキルの証明として認められるこの検定は、今後も全社的に推奨していく方針です。
<学習支援>社員にどの教材を提供しましたか?教材の使い勝手はいかがでしたか?
業務と学習を両立させるために会社として実施したことはありますか?
当法人では、パート社員を含む全スタッフのスキルアップを目的に、以下の教材・講座を整備し、自主学習を支援しています:
- 2級対策講座(WEB講座)
- 2級模擬試験講座(WEB講座)
- 2級公式テキスト
- 1級対策講座(WEB講座)
- 1級模擬試験講座(WEB講座)
- 1級公式テキスト
これらの教材は、初学者から実務経験者まで幅広く活用でき、特に模擬試験講座は「実務に近い場面設定で応用力が養える」と好評です。
さらに、検定直前には社労士講師による対面での勉強会(直前対策会)を実施し、頻出テーマの整理や質疑応答の場を設けました。「現場で曖昧だった知識が腑に落ちた」「不安が解消され自信を持って受験できた」との声が多数寄せられています。
また、受験推奨にあたっては、制度として押しつけるのではなく、すでに受験・合格したメンバーの「実務に役立つからこそおすすめしたい」というリアルな声が、新たな挑戦者の背中を押しています。こうした“自走する学びの文化”が、社内に根づき始めています。
<実績>御社で受験なさった方の平均的学習期間や合格率をお教えください
当法人における給与計算実務能力検定の受験状況について、以下の通りご参考までに共有いたします。
- 2級合格率:100%(全員1回目で合格)
- 1級合格率:初回合格80%、2回目で全員合格(最終的に100%)
学習期間の目安は以下の通りです:
- 2級:おおよそ20〜30時間
- 1級:おおよそ40〜50時間
当法人では日頃から給与計算実務に直接携わっているスタッフが多いため、学習内容と業務の親和性が高く、比較的スムーズに学習が進んでいる傾向があります。検定対策が「実務の棚卸し」や「理論の裏付け」として機能していることも、高い合格率と短期間での習得につながっている要因の一つと考えています。
<効果>検定を社員に学習・受験させたことでどのような効果があり、今後何を期待しますか?
この検定の学習・取得を通じて、社員・パートを問わず「根拠を持って判断し、説明できる力」が着実に育っています。
これまで上司や社労士のダブルチェックが前提だった業務も、自ら判断・処理できるスタッフが増えたことで、業務のスピードと正確性が大きく向上。確認・修正の工数が減り、お客様へのレスポンスもより迅速になりました。
また、当法人では「自ら学び、自ら考え、粘り強く行動できる人材」を育成の柱としています。この検定は、その姿勢や成長を可視化できる指標として非常に有効であり、昇給や評価にも活用しています。
さらに、当法人では給与計算実務能力検定1級の合格を、全スタッフに必須とする方針を定めています。検定合格はあくまで通過点と位置づけ、より高いレベルで専門性を発揮できるよう、合格後も知識のアップデートや実務研修を継続しています。
給与計算の品質が企業経営の信頼性に直結する今、私たちは「給与計算のプロ集団」として、全国の中小企業の頼れるパートナーであり続けることを目指しています。


 「給与計算実務能力検定試験®」に合格するための公式対策講座
「給与計算実務能力検定試験®」に合格するための公式対策講座
 「給与計算実務能力検定公式DVD講座」について。
「給与計算実務能力検定公式DVD講座」について。
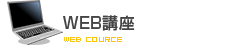 「給与計算実務能力検定公式WEB講座」について。
「給与計算実務能力検定公式WEB講座」について。
 「給与計算実務能力検定試験®」について学ぶための公式テキストです。
「給与計算実務能力検定試験®」について学ぶための公式テキストです。
 初めて給与計算をする人のための給与計算入門講座です
初めて給与計算をする人のための給与計算入門講座です
 「給与計算」という業務について分かりやすくご説明します
「給与計算」という業務について分かりやすくご説明します